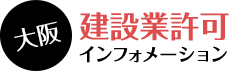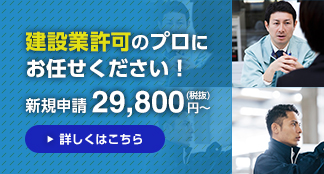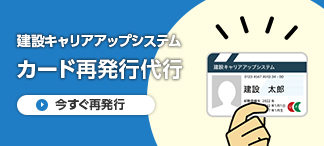建設業許可のこわーい話~許可飛んだ 許可飛びそう その1~
2018.12.29更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
今年ももうすぐ終わっちゃいますねー。この一年色々な方に出会い、話、飲みました。リーマン時代には味わえなかったストレスや喜びがあったので非常に勉強にもなったし、振り返れば良い年だった気がします。
という訳で今年恐らく最後の記事になりますが、日頃ご愛読いただいている方のために建設業許可のこわーい話をしたいと思います。当たり障りのない記事書いてもしゃーないですしね。
それでは建設業のこわーい話の始まりです!震えながら見てくださいね。
目次
やっとの思いで建設業許可が取れたわー。もうこれで安泰安泰♪
何をもって安泰かはわからんですが、安泰ちゃいますよー。
確かに建設業許可を取得すれば500万以上の工事が出来るようになるし、最近の流行している元請け業者からの現場入場規制にもひっかかりません。それはスゴクいいこと。事業拡大の一歩ですしな!
しかし、同時に建設業許可を取得するとこわーい話も出てきます。
ちょっとずつ事例を紹介していきましょか。
①許可業者なのに欠格要件に該当してしまった!
許可取得後、欠格要件に該当してしまうと許可の取り消し処分を受けます。
まずは許可持ってる建設業者のどの立場の人がやっちゃったら許可がお亡くなりになるかを見ていきましょう。
個人事業主
代表者、営業所の所長、支配人が該当するとグッバイ建設業許可です。
法人
取締役、営業所の所長、相談役、顧問、法人の場合には5%以上を出資している株主が該当するとグッバイ建設業許可です。※監査役はダイジョブです。
本題に入ります。
実はこれ一番気をつけなアカンとこなんですけど行政書士さんってこの辺の説明してるんですかね。以前、問い合わせで執行猶予ついちゃったんですけど、大丈夫ですかね?っのもあったなー。
新規で許可取得する場合は執行猶予期間が満了したときに、刑の言い渡し自体がなかったことになるんで、執行猶予期間が満了したときは期間が終わったときに申請すればいいですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。よってせっかく苦労して取ったのに更新申請の際、建設業許可はお亡くなりになりますので、許可業者ではなくなります。
自分とこの従業員がやっちゃた場合は許可には問題ないので、早朝から深夜までお説教してあげてください。執行猶予は社会復帰への道ですから卒業させなくても良いので。
さてこの執行猶予ってどんな時につくか。イメージできる人なかなかおらんと思いますので、チョビット解説しときます。
執行猶予の解説
執行猶予が付されるのは、懲役ないし禁錮3年以内の刑罰の場合で、それ以上の長期刑は執行猶予がつきません。
ほんで、執行猶予を受けられる被告人は、
- ①初犯である
- ②(罰金)前科・前歴のみである
- ③執行猶予付きの判決を受けたことがあっても、取消しがなく執行猶予期間が経過している
- ④実刑判決を受けても、刑期の終了から5年が経過している
- ⑤執行猶予期間でも、ある一定の条件を満たしている
のどれかに該当する必要があります。
この時期飲酒運転とか酒がらみの小突きあいをチョイチョイみます。
執行猶予になったら全て台無し、取引先が手を引く、従業員の給料払えない、子供の学費や生活費が払えないって状況にもなりかねないので注意しましょう。
ちなみに、このページに飛んできた人の中にはもしかしてですけどやっちゃった方もおられるかもしれません。バレルかバレないかが当然気になるところだと思います。。。
建設業の更新申請をした時に、役員等の犯歴を警察に照会されるので、執行猶予中なのかどうかバレます。キレイにバレます。窮地に追い込まれると、人間てのは都合のいいように物事を解釈しちゃうので、もしかしたら裏技があるんちゃうか。。。ってことを考えると思いますが、バレるので安心してください。
②許可番号が変わった!
建設業許可の番号は、年度のとこ以外、基本変わることはないです。
複数の工事業種について建設業許可を取得したとても許可番号は変わりません。
どういった場合、許可番号は変わるのか。それは廃業して新規で取り直した場合です。
実際にこういったことがあったかどうかは知らんけど、下記のようなパターンあったら怖いですよねー。
ショートストーリー
元請業者のAさんは、苦労して建設業許可を取得した下請けのBさんに長年、発注してました。
Aさんの現場に入る際には許可番号、業種、技術者等色々書いてもらってます。
Bさんを信頼しているAさんは普段あまりそこを見なかったんですが、ある日、なんとなーく見たら許可番号が変わっていました。
Bさんに聞くと『ちょっとやっちゃいまして、許可が取り消しになってたんすよー!あ、でも今は新しく持ってるんでダイジョブっす!』
そこでAさんは青ざめました。一定の期間、許可業者じゃなかったBさんに500万以上の工事を発注していたのです。
さてこのショートストーリーで一番怖いのは軽いノリのBさんじゃなく、
建設業の許可を受けた建設業者に建設工事を施工させるべき場合において、許可を受けていない建設業者に工事の施工をさせたAさんです。
俗にいう建設業法3条違反です。Bさんもアウト中のアウトですが、この場合はAさんに同情するのでBさんは割愛します。この場合、Aさんは100万円以下の罰金となりますので1COMBO。
さらに欠格要件の一つである建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられたものに該当しますので許可も飛んで2COMBOです。K・O(許可・終わった)です。
さらに言うとゼネコンさんの中にはICカードを発行、許可番号で管理している所もあるかもなので、許可番号変われば再発行等がいるかもです。想像したら分かると思うんですけど、これヒジョ―に信頼が失墜しますよね。
元請さんも暇じゃないし、再登録・再発行もメンドクサイし、事情によっては元請も上記のようなCOMBOくらう可能性もありますしね。もういっちょ追加すると公共工事を請けるために経審とったときも同様ですよね。
許可が飛んだらどうなんの??
簡単に言うと許可取る前に逆戻りです。
なので500万以上の工事は請けれないことになります。
しかもこれが従業員そこそこ抱えてるとこだと、今まで通りの工事を請け負えないので、卒業等の非常に厳しい経営判断が必要になってくるかもです。まぁまた取り直せばいいって話にもなると思いますが、上記で説明した現象になる可能性があるので注意しましょう。
書いてて震えが止まりませんわ。
終わりに
久しぶりの更新ですが、しばらくは建設業のこわーい話をやっていこうかなと思ってます。
チラ見でも良いのでこの記事を呼んで建設業者さんの気が引き締まってくれることを切に願います。
それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。