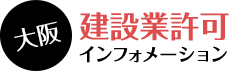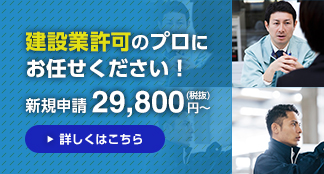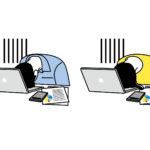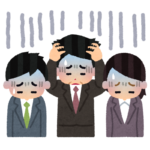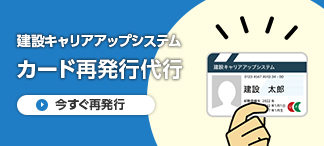建設業許可を個人事業主で取得するために、【知っておくべき5つのポイント】
2019.06.20更新

まずハッキリ言います。
個人事業主の建設業許可取得は簡単ではありません
個人事業主で、1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事のみ(軽微な工事)を請け負って生計を立てている方はたくさんいると思います。
しかし最近では、建設業許可が不当な工事の請負であるにもかかわらず、元請業者から建設業許可の取得を求められることが多くなっていませんか?
それに融資を受けようとすると、建設業許可の取得が融資の条件に追加されるなんて話もよく聞きます。軽微な工事のみの請負であっても、許可を取得せずに建設工事で生計を立てていくのは難しくなっていく時代になりつつあります。
そこで、建設業許可がどうしても必要となった時に頭を抱えることなく許可申請ができるよう、今からでも準備を進めてもらいたいという趣旨で、経営管理業務責任者について知っておくべき5つのポイントをお伝えいたします。
目次
ポイント① 許可申請をするために求められる書類のハードルは非常に高い
さて、個人事業主の方が行政書士に依頼をして、建設業許可申請ができる確率ってどのくらいか想像できますか?
許可取得ではなく、許可申請が出来る確率です。
行政書士に依頼するのだから、当然に100%だと思いますか?
それとも行政書士と言えども、80%くらいだと思いますか?
私の経験上のお話ですが、個人事業主の経験をもって難なく建設業許可申請ができる確率は5%~10%くらいです。
行政書士の能力云々の話ではありません。
単純に、個人事業主が許可申請をするために求められる書類のハードルが高いのです。
今回は、建設業許可を取得するための要件のひとつである「経営業務の管理責任者」となるために必要な書類について、どのような書類が必要なのかを解説していきます。
ポイント② 経営業務の管理責任者となるためには経験期間と「経験内容」を証明する書類を準備する
建設業の許可を取得しようとする場合は、一定の条件を満たす経営業務の管理責任者となる人が必要です。
そして、経営業務の管理責任者となる条件を満たしていることは書面で証明する必要があります。
経営業務の管理責任者となるための一定の条件
- ① 取得しようとする建設業種に関する経営経験が5年以上あること。
- ② 取得しようとする建設業種以外の業種に関する経営経験が6年以上あること。
個人事業主の方は、10年~20年以上の経験をされている方も多いので、楽勝でクリア出来ていると思った方も多いんじゃないでしょうか?
残念ながら実際はそんなに簡単な話ではありません。
大変なのは、その経営経験を「書面で」証明しなければならないところにあります。
いくら口頭で経験があると言っても、行政庁は書面がないと信じてくれません。
口頭だけで信じてしまうと誰でも簡単に経営業務の管理責任者になれてしまうからです。
経営業務の管理責任者となるためには、「経験期間」を証明する書類と「経験内容」を証明する書類を準備しなければなりません。
ポイント③ 経験期間を証明する書類を知る
経営業務の管理責任者となるためには、5年~6年以上の経営経験期間を証明する必要があります。
通常、その経験期間分の「受付印付きの確定申告書控えの原本」を準備することになります。
最近は電子申告が増えているので、その場合は申告書と受付されたことが分かる画面(「メール詳細」という画面)を印刷すれば、税務署に受付されたことを証明できます。
ポイント④ 経験内容を証明する書類を知る
経営経験期間が証明できたとして、その期間中、建設業を営んでいたこと(具体的な内容)を証明する書類も準備する必要があります。
具体的には、建設工事の請負契約書や注文書と請書のセット(原本)、もしくは請求書の写しと入金記録(通帳の原本)などを5年~6年以上分、準備することとなります。
また管轄行政庁によって、提出を求められる書類の量や内容は異なります。
例えば、大阪府では工事と工事の間隔が12か月以上空かないように、年1件程度×経験年数の請負契約書等が必要となります。
※年1件の経験で足りるという意味ではなく、経験があることを前提に提出する書類は年1件としているだけです。
ポイント⑤ 必要書類は意外と揃わない
冒頭で経験上、建設業許可申請ができる確率は5%~10%くらいと言いましたが何故そのような低い確率になってしまうのか…。
それは、上記書類がすぐに揃うことがほとんど無いからです。
例えばですが、経験年数分の確定申告書の控え原本はすぐに準備できるでしょうか?そもそもキチンと確定申告をしていますか?
紛失している場合は、税務署から写しを開示請求する方法も考えられますが、それには1ヶ月ほどの時間を要しますし、必要としている期間の写しの全てが開示されるかどうかも不明です。
より難しいのは、通年分の請負契約書等の原本の準備です。
そもそも、請負契約書を毎回取り交わしていますか?
注文書をFAX等で受信して、請書は作成していますか?
請求書をしっかり発行していたとして請負金額を手渡しで受領していませんか?
請負契約書等が存在しないと、経験内容の確認はできませんよね?
請負金額を手渡しで受領していると、入金確認はできませんよね?
請負契約書等を作成されていたとしても、5年~6年分の書類をすぐに用意できますか?
建設現場に出る前や帰宅後に準備いただくので、それだけでも非常に時間がかかります。問題なく許可申請をすることがいかに難しいか、なんとなくですがお分かりいただけたかと思います。
終わりに
最後に、今回の解説をもう一度確認しましょう。
知っておくべき5つのポイント
- ポイント① 許可申請をするために求められる書類のハードルは非常に高い
- ポイント② 経営業務の管理責任者となるためには経験期間と「経験内容」を証明する書類を準備する
- ポイント③ 経験期間を証明する書類を知る
- ポイント④ 経験内容を証明する書類を知る
- ポイント⑤ 必要書類は意外と揃わない
許可取得には入念な準備が必要です。
現状を一刻でも早く打破したい、もう悩みたくないという方は、是非お問い合わせください。

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。